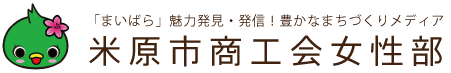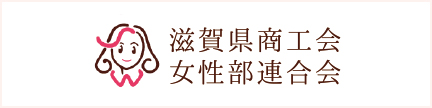醒井の静かな町並みに佇む「丁子屋製菓」。この店には、和菓子職人として始まった家族の歴史と、時代の流れに合わせて新たな挑戦を続ける姿が詰まっています。和菓子、洋菓子、パンと移り変わる中で、「手作り」という原点を守り続ける家族の物語をお届けします。今回は娘さんの服部悠さんにお話を伺いました。

和菓子からパンへの大転換:伝統に新風を吹き込む
「丁子屋製菓」はもともと和菓子店として始まりました。ひいおじいさんが和菓子屋を開業し、その後、おじいさんとお父さんへと受け継がれていきます。しかし、お父さんが洋菓子の修行から帰ると、時代の流れに合わせて和菓子から洋菓子、そしてさらにパン作りへと大きな転換を図りました。
パン屋への転換の裏にはこんなエピソードがあります。ある日突然、父親が修行に出て1~2ヶ月姿を消したかと思えば、戻ってきた時には店がパン屋へと改装されていました。家族や地元の人たちもその変化に驚きましたが、長年の努力で少しずつパン屋のイメージが根付いてきました。
「パン屋として馴染むまでにかなり時間がかかりましたね。30年以上経った今でも、『和菓子屋さんのイメージが強い』と言われることがあります。でも、その両方があるからこそ、お客様に驚いてもらえる店になっているのかなと思います。」と語る悠さん。

仕事への情熱:小さい頃から見続けた家族の背中
悠さん自身も高校卒業後、父親の影響を受けてケーキ屋の道へ進みました。「父が和洋菓子をしていた頃から、ずっとお菓子作りに憧れていました。『作ること』が好きなんだと思います。」と振り返ります。20年近くケーキ屋での勤務経験を積み、結婚を機に地元へ戻った悠さん。
家業を手伝い始めた当初は、「ほんの少しだけ」という気持ちでしたが、気づけば今ではパン作りの担当を一手に引き受ける存在に。朝早くから夜遅くまで働く日々が続きますが、「好きだから続けられる」と話します。仕事を通して自分らしい生き方を楽しまれている様子が伝わります。
子供の頃の悠さんにとって、家業を手伝うことは「嫌だった」と言います。受験生だった時にパン屋をオープンし、手伝わざるを得なかったり、クリスマスには家族でケーキを70個近く作ったりと、子供ながらに過酷な毎日でした。しかし、大人になった今、その経験があったからこそ店を維持するための段取りや工夫を学んだと振り返ります。

手作りへのこだわりとお客様の支え
現在、丁子屋製菓は和菓子とパンの両方を提供するユニークな店です。和菓子は弟さんが中心となって新商品を開発し、悠さんはパン作りを担当しています。「手作り」が基本で、食パンやクルミパンなど、地元でも評判の商品を提供しています。特にクルミパンは、「普通のクルミパンよりもクルミがたっぷり入っている」と驚かれることもしばしばです。
また、季節ごとに変わるどら焼きも人気の商品です。中に入れるあんを変えるなど、工夫を凝らした商品は地元だけでなく観光客にも好評。夏場にはソフトクリームや水まんじゅうが加わり、冬にはお餅や鏡餅を提供するなど、季節ごとに店の顔が変わります。
「地元の人から『やっぱり丁子屋製菓さんだな』と言ってもらえるのが嬉しいです。観光客が多い夏場でも、夕方になると地元の人たちが顔を出してくれるんです。そういう支えがあるから頑張れますね。」

仕事と家族の絆:支え合いながら続けていく
家業を続ける中で、家族の協力は不可欠です。「いざという時に頼れるのは家族」と語る悠さん。悠さんのご主人も地蔵盆や地元のマルシェの手伝いに来てくれるそうです。「本当にありがたい」と感謝の言葉を繰り返します。
お父さんが現役を引退したら、「自分たちのやりたいようにやればいい」と言われているそうですが、悠さんは「父や祖父が守ってきたものを壊したくない」と考えています。時代の変化に合わせた工夫をしながらも、店の根幹である「手作り」を守り続けていきたいという想いが強いのです。

変わらないために変わり続ける:丁子屋製菓のこれから
悠さんは、「お店を大きくしたいとか、目立ちたいとか、そういう野心はありません。ただ、期待を裏切らないお店でありたい。」と語ります。
家族で支え合い、伝統を守りながらも、時代のニーズや流行に柔軟に対応する。それが「丁子屋製菓」の変わらない強さであり、地元からも観光客からも愛される理由です。
「父や祖父がやってきたことを続けていきたい。そして、私たちの味を忘れずに、毎年『またここで』と言ってもらえるお店でありたい。」その穏やかな口調から、家族と仕事への愛情が感じられました。

醒井の町に訪れる際にはぜひ、「丁子屋製菓」の手作りの味を楽しんでみてください。きっとそこには、家族が紡いできた伝統と情熱が詰まっています。